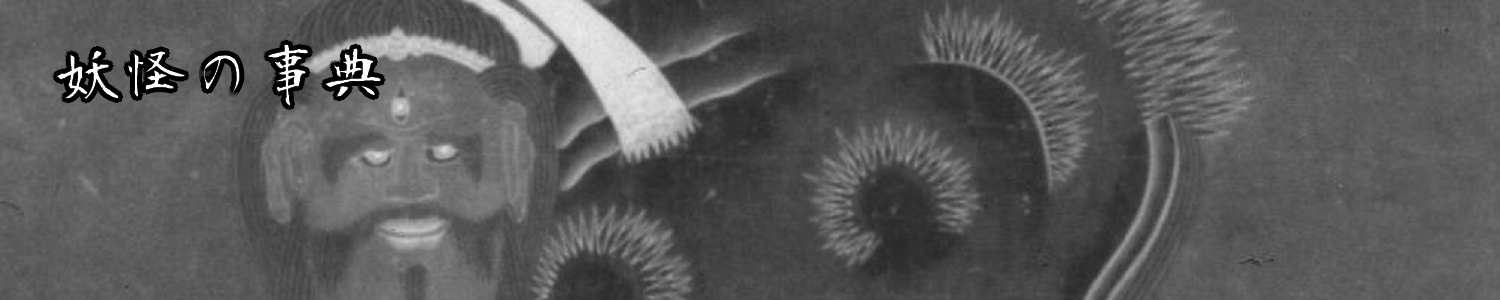|
【かわうそ】
日本各地に伝わる妖怪。
一般的な動物としても知られており、分類上は食肉目イタチ科に属します。
 獺の概要 獺の概要
江戸時代の『和漢三才図絵』や『百物語評判』などにも記載があります。
小さな狗のようなもので、四足が短く、毛は薄青。よく魚を獲り、美童や美女に化けるそうです。
地方によっては河童と同一視されていることもあり、獺と相撲をとる話などが残っています。
 獺の伝承・逸話 獺の伝承・逸話
青森県
〇川獺は人をだます、怖し、之にだまさるれば、やつが脫けて人は愚物のやうになる(末廣)やつとは精根元氣をいふらし。又いふ、川獺は生首に化け、夜、かじか掬きに徃けば網に此生首のかかることありと(黒石)
『津輕口碑集』: 126ページ 內田邦彥 鄕土研究社 1929
東京都
徳川の家来に福島何某という武士がありました。ある雨の夜でしたが、虎の門の濠端を歩いていました。この濠のところを俗にどんどんといって、溜池の水がどんどんと濠に落ちる落口になっていたのです。
その前を一人の小僧が傘もささずに、びしょびしょと雨に濡れながら裾を引き摺って歩いているので、つい見かねて「おい、尻を端折ったらどうだ」といってやりましたが、小僧は振り向きもしないので、こんどは命令的に「おい、尻を端折れ」といいましたが、小僧は相変わらず知らぬ顔をしています。で、つかつかと寄って、後ろから着物の裾をまくると、ぴかっと尻が光ったので、「おのれ」といいざま襟に手をかけて、どんどんの中へ投げ込みました。
が、あとで、もしそれが本当の小僧であっては可哀相だと思って、翌日そこへ行って見ましたが、それらしき死骸も浮いていなければ、そんな噂もなかったので、まったくかわうそだったのだろうと、他に語ったそうです。
芝の愛宕山の下〔桜川の大溝〕などでも、よくかわうそが出たということです。
それは多く雨の夜なのですが、差している傘の上にかわうそが取りつくので、非常に持ち重りがするということです。そうして顔などを引っ掻かれることなどがあったそうですが、武士などになると、そっと傘を手許に下げておよその見当をつけ、小柄を抜いて傘越しにかわうそを刺し殺してしまったということです。
中村座の役者で、市川ちょび助という宙返りの名人がありました。やはり雨の降る晩でしたが、芝居がはねて本所の宅へ帰る途中で遭ったそうです。差している傘が石のように重くなって、ひと足も歩くことができなくなったので、持前の芸を出して、傘を差したまま宙返りをすると、かわうそが大地に叩きつけられて死んでいた、ということです。
『風俗江戸物語』「江戸の化物」 岡本綺堂 贅六堂 1922
【底本】『風俗江戸東京物語』(河出文庫): 79-80ページ 岡本綺堂 河出書房新社 2001
新潟県
斑雪が降る夜のこと。ホトホトと戸を叩かれ、12、3歳くらいの子供の声で「おつかれでござんしょ」と聞こえます。戸を開けると、くしゃみをしながら、雪の中をピチャピチャと歩いて逃げていく者があったそうです。
また、提灯の火を取るとか、尾で殴ってくるともいいます。小便をすればカワウソの害を避けられるとされています。
佐渡郡佐和田町にもカワウソの話が伝わっています。
馬の背中に乗っていたカワウソが捕まってしまい、毎朝3匹の魚を届けると約束をして許されました。しかし、やがて川の魚を取り尽くしてしまって、とうとう餓死してしまいました。
石川県
能登でも河獺は二十歳前後の娘や、碁盤縞の着物を着た子供に化けて來る。誰だと聲かけて人ならばオラヤと答へるが、アラヤと答へるのは彼奴である。又おまへは何處のもんぢやと訊くと、どういふ意味でかカハイと答へるとも謂ふ。
『日本評論』11巻3号「妖怪談義」 柳田國男 1938
【底本】『妖怪談義』(現代選書): 20ページ 柳田國男 修道社 1956
島根県
(イ)獺の證文
出雲國八束郡西川津村には、獺の證文を祀る社がある。
昔、此處の河で、岸に草を食つてゐる馬の手綱を、自分の腰に卷きつけて、水の中へ引込まうとした河獺があつた。馬は驚いて、飛上つて、一走りに走つて、二三町距れた綿畑の中へ駈込んだ。流石の河獺も、これには面喰つて、綿畑の中を、馬に引摺られて、轉がり廻つてゐると、仕事をしてゐる村の者が、それを見つけて、それ、川子、川子と騒ぎたてる。河獺は、腰に手綱を縛りつけてゐるので、逃げることが出來ず、到頭村の者に捕へられる。日頃の仇、思ひ知れと、村の者が河獺を撲殺さうとすると、河獺は縮みあがつて、手を合せて拜む。村の者が、不憫に思つて、助けてやると、河獺は其まゝ村に奉公して、田や畑の仕事をする。けれども、河獺は元來、人間の生膽を拔くのが好きである。村に奉公してゐても、此癖が中々止まないで、稍ともすると、村の者の臀のあたりに、手を出したがる。始めの程は、瓦の片を當てゝ、用心をしてゐたが、村の者も、餘り度々のことに、後では氣味が惡く成つて、種々相談をした後で、河獺に證文を入れさせて、暇をやる事にする。河獺も非常に喜んで、此後、水に溺れた者があつても、「雲州西川津村」、と三度呼びさへすれば、決して生命を取るやうなことはせぬ、と誓つて、河へ歸った。
宮に祀つてあるのは、此時の證文である。今でも、土地の者は、水泳の時に「雲州西川津」と唱へる。川子除の呪文である。(清水兵三君)
『日本傳說集 分類總目次解說索引附』: 127-128ページ 高木敏雄 鄕土研究社 1913
広島県
広島市では「伴の川獺」「阿戸の川獺」などと称され、大坊主に化けると伝えられています。
高知県
河童のことをカワウソと呼んでいます。
相撲を好みますが、頭を揺らして水をなくしてしまえば弱体化します。また、前足が短く、坂を上るときは早いのですが、坂を下りるのはよぼよぼしているそうです。
|