|
【ゆうれい】
死者の霊魂が姿を現したもの。
 幽霊の概要 幽霊の概要
肉体を失った死者が姿を現した話は日本及び世界各地にあります。
「四谷怪談」「皿屋敷」「牡丹燈籠」の三作は日本三大怪談に数えられ、いずれも霊が恐怖を掻き立てる物語となっています。
死んだ女が赤ん坊のために飴を買いにくる子育て幽霊の話も有名で、北は青森県から南は沖縄県まで、広い範囲で伝えられています。
日本の幽霊は足が見えない姿で想像されることも多いのですが、これは円山応挙が描いた幽霊画の影響だとする説もあります。
 「幽霊」と「妖怪」の関係 「幽霊」と「妖怪」の関係
幽霊という存在は、妖怪とは区別されるものだとする主張があります。
例えば柳田國男は『妖怪談義』の文中で、都市の居住者の中には化け物の話をする者が多いが、彼らは幽霊をオバケと混同しているとし、オバケと幽霊の違いを次のように説明しています。
誰にも氣のつく樣なかなり明瞭な差別が、オバケと幽靈との間には有つたのである。第一に前者は、出現する場處が大抵は定まって居た。避けてそのあたりを通らぬことにすれば、一生出くはさずに濟ますことも出來たのである。これに反して幽靈の方は、足が無いといふ說もあるに拘はらず、てく/\と向ふから遣つて來た。彼に狙はれたら、百里も遠くへ逃げて居ても追掛けられる。そんな事は先づ化物には絕對に無いと言つてよろしい。第二には化け物は相手を擇ばず、寧ろ平々凡々の多數に向かつて、交渉を開かうとして居たかに見えるに反して、一方はたゞこれぞと思ふ者だけに思ひ知らせようとする。従うて平生心掛けが殊勝で、何等やましい所の無い我々には、聽けば恐ろしかつたろうと同情はするものゝ、前以て心配しなければならぬ樣な問題では無いので、たま/\真っ暗な野路などをあるいて、出やしないかなどゝびく/\する人は、もしも恨まれるやうな事をした覺えが無いとすれば、それはやはり二種の名稱を混同して居るのである。最後にもう一つ、これも肝要な區別は時刻であるが、幽靈は丑みつの鐘が陰にこもつて響く頃などに、そろ/\戸を敲いたり屛風を搔きのけたりするといふに反して、一方は他にも色々の折がある。器量のある化け物なら、白晝でも四邊を暗くして出て來るが、先づ都合のよささうなのは宵と暁の薄明りであつた。人に見られて怖がられる爲には、少なくとも夜更けて草木も眠るといふ暗闇の中へ、出かけて見た所が商賣にはならない。しかも一方には晩方の幽靈などゝいふものは、昔から聽いたためしが無いのである。大よそこれほどにも左右別々のものを、一つに見ようとしたのはよく/\の物忘れだと思う。だから我々は怪談と稱して、二つの手をぶら下げた白裝束のものを喋々するやうな連中を、よほど前からもうこちらの仲間には入れて居ないのである。
『妖怪談義』(現代選書): 16-17ページ 柳田國男 修道社 1956
要約すると、オバケと幽霊には次のような違いがあるというのが柳田の見解です。
オバケ(化け物)
・出る場所が定まっている。
・相手を選ばずに現れる。
・出る時刻は宵と暁の薄明りの頃(器量があれば白昼でも辺りを暗くして出る)。
幽霊
・向こうからやってくる。逃げても追いかけてくる。
・これぞと思う者のもとに現れる。
・出る時刻は丑みつ時。
ここで柳田が用いているオバケや化け物という言葉が「妖怪」と同義か否かは判断しにくいのですが、一般にこの文章は妖怪と幽霊の違いを示したものだと解釈されています。
「これほどにも左右別々のものを、一つに見ようとしたのはよく/\の物忘れだと思う」「二つの手をぶら下げた白裝束のものを喋々するやうな連中を、よほど前からもうこちらの仲間には入れて居ない」と、やや攻撃的とも受け取れる言葉を使って非難しているあたり、柳田はオバケの中に幽霊を混在させられるのがよほど嫌だったのでしょう。
しかし、江戸時代の絵巻や図譜を見ると、幽霊とその他の妖怪が分け隔てなく掲載されている作品も少なくありません。
『化け物づくし』、『化物絵巻』、佐脇嵩之の『百怪図巻』には、著名な妖怪とともに幽霊が並べられています。鳥山石燕の『画図百鬼夜行』も同様で、死霊や幽霊が収録されています。
柳田の言に従うならば、江戸の絵師たちもまた「よく/\の物忘れ」だったということなのでしょうか……?
 幽霊の画図 幽霊の画図
【幽霊の画図が掲載されている主な資料】
| 資料名 |
作者 |
制作年 |
妖怪名 |
画像 |
| 『化物づくし』(個人蔵) |
不明 |
不明 |
幽霊 |
|
| 『百怪図巻』(福岡市博物館蔵) |
佐脇嵩之 |
1737 |
ゆふれゐ |
画像 |
| 『画図百鬼夜行』前篇 陽 |
鳥山石燕 |
1776 |
幽霊 |
画像 |
| 『化物絵巻』(川崎市市民ミュージアム蔵) |
不明 |
1800年代前半? |
ゆふれい |
|
|


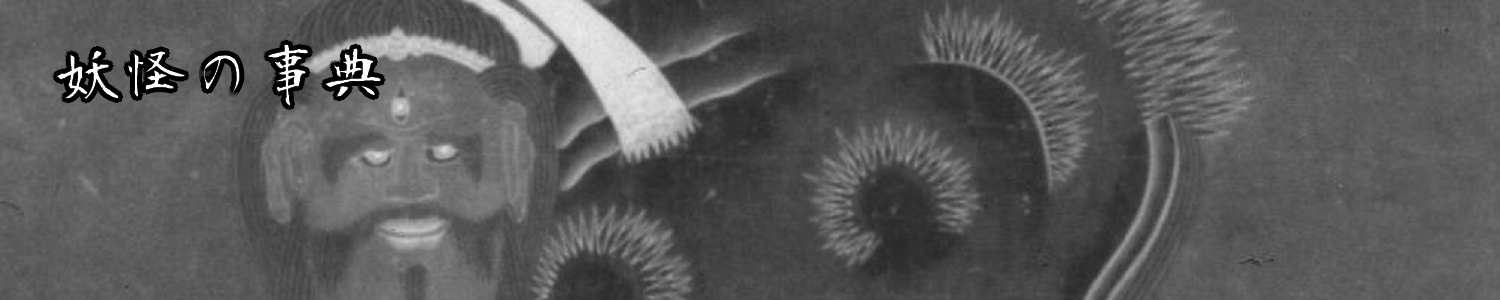
![]() 主な参考資料
主な参考資料