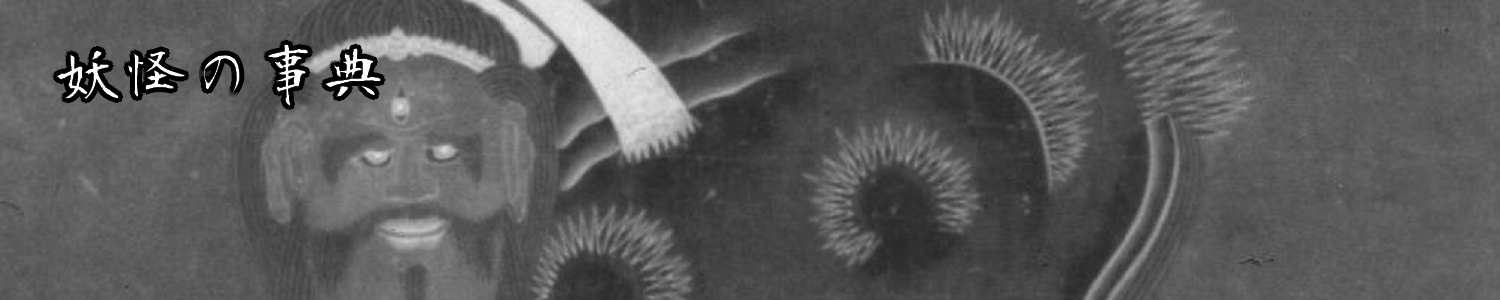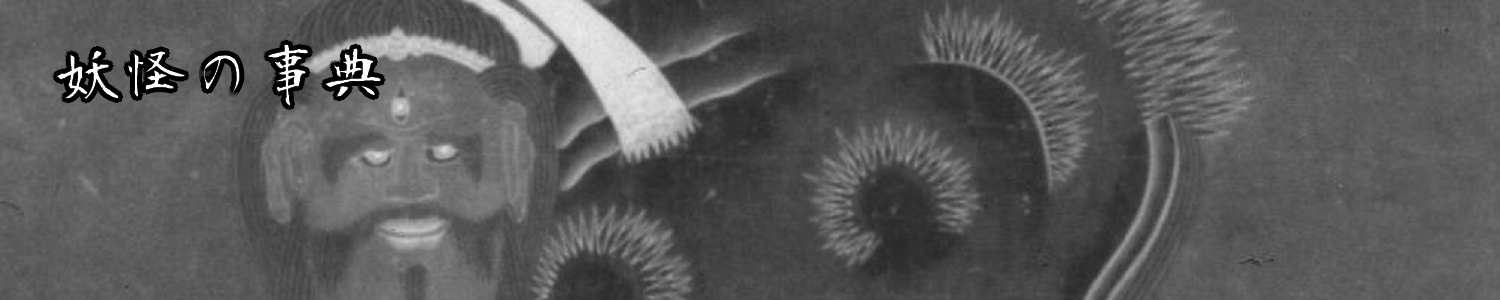
 橋姫 橋姫
|
【PR】
|
|
【はしひめ】
橋に祀られている女神。
 橋姫の概要 橋姫の概要
古い大きな橋などに祀られている神であり、橋の守護神、また敵の侵入を防ぐ塞の神だとされます。
元々は水神信仰の一環で、男の神と女の神を橋の袂に祀ったことが起源だったと考えられています。
非常に嫉妬深い神で、橋の上で別の橋を褒めた者や、女の嫉妬を描く『葵の上』『野宮』といった謡をうたった者を恐ろしい目に遭わせるといいます。これは「愛らしい」を古語で「愛し」といい、愛人のことを「愛し姫」と呼んだことにちなんでいるそうです。
京都府宇治市にある宇治橋の橋姫が特によく知られています。
以前は宇治橋の南側の欄干にある「三の間」という張り出しに祀られていました。この場所で美男子が川を眺めていると、橋姫に見初められて川に引き込まれてしまうといわれていたのだとか……。
現在では橋姫神社で祀られています。
『艶道通鑑』には宇治の橋姫の由来が記されています。
とある司の長男である男性が、隣家の女と夫婦になる約束を交わしたにもかかわらず、別の娘と契ってしまいました。隣家の女は激怒し、貴船神社に参詣。それから七日七晩に渡って宇治川に浸かり、生きたまま鬼になりました。そして男性を取り殺し、さらに彼の一族をも呪い殺したのです。人々は怨霊を鎮めようと、橋姫として宇治橋に祀りました。橋姫は嫉妬深いので、婚礼のときには宇治橋を通らないようにしたそうです。
鳥山石燕の『今昔画図続百鬼』(1779)にも橋姫の姿が描かれ、次のように解説されています。
橋姫
橋姫の社は山城の国宇治橋にあり 橋姫はかほかたちいたりて醜し 故に配偶なし ひとりやもめなる事をうらみ 人の縁辺を妬給ふと云
『今昔画図続百鬼』上之巻 雨 鳥山石燕 1779
宇治橋の他には、摂津の長柄橋や近江の瀬田橋などにも橋姫が祀られていたそうです。
|

『今昔画図続百鬼』上之巻 雨「橋姫」 鳥山石燕 1779
|
|
 主な参考資料 主な参考資料
[文献]
『幻想世界の住人たち』IV 日本編(Truth In Fantasy): 137-140ページ 多田克己 新紀元社 1990
『鳥山石燕 画図百鬼夜行』: 116ページ 高田衛 監修、稲田篤信 田中直日 編 国書刊行会 1992
『妖怪事典』: 272-273ページ 村上健司 毎日新聞社 2000
|

|