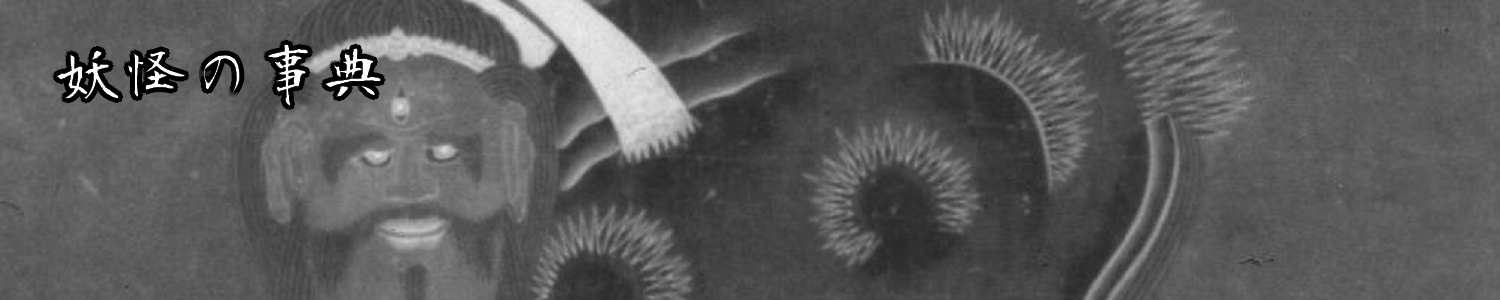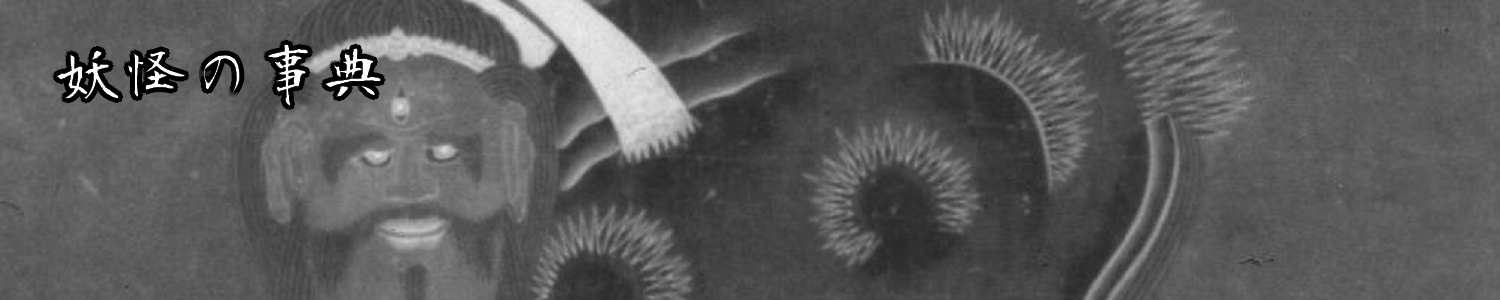
 般若 般若
|
【PR】
|
|
【はんにゃ】
能に見られる鬼女の面のこと。
 般若の概要 般若の概要
般若の分類
能において、般若は生成、中成、本成に分けられています。
生成とは『鉄輪』の人妻が分類されるもので、怒りと悲哀が混在した醜女だといいます。
中成には、『葵上』の白般若(高貴で色白の女が成る)、『紅葉狩』の赤般若(怒りで顔を赤くする)、『安達原』の黒般若があります。
そして、怒りで蛇体と化す『道成寺』が本成なのだそうです。
般若の語源
仏教でいう般若という語は、真理を認識して悟りを開く最高の智慧を意味するサンスクリット語のプラジナ(鉢羅若那)から来ているとされます。
『大般若波羅蜜多経』はそうした智慧として諸法皆空の理を説いたものであり、これを簡潔にしたものが『般若心経』なのです。
般若が鬼女と結びついた背景には謡曲『葵上』があると考えられます。
生霊と化して葵上を苦しめる六条御息所を退散させるため、聖が経を読むと、それを聞いた六条御息所は「あらあら恐ろしの般若声や」と言って去ります。この話にちなみ、六条御息所がつけていた鬼面が般若と呼ばれるようになったらしいのです。
鳥山石燕の『今昔画図続百鬼』(1779)にも次のように解説されています。
般若
般若は経の名にして苦海をわたる慈航とす しかるにねためる女の鬼となりしを般若面といふ事は 葵の上の謡に 六条のみやす所の怨霊行者の経を読誦するをきゝて あらおそろしのはんにや声やといへるより転じて かくは称せしにや
『今昔画図続百鬼』上之巻 雨 鳥山石燕 1779
ただし、江戸時代の随筆『嬉遊笑覧』には異説も見られます。
それによれば、南都の僧である般若坊が鬼女の面を作ったことに由来するのだとか……。
|

『今昔画図続百鬼』上之巻 雨「般若」 鳥山石燕 1779
|
|
 主な参考資料 主な参考資料
[文献]
『鳥山石燕 画図百鬼夜行』: 117ページ 高田衛 監修、稲田篤信 田中直日 編 国書刊行会 1992
『妖怪事典』: 277ページ 村上健司 毎日新聞社 2000
|

|