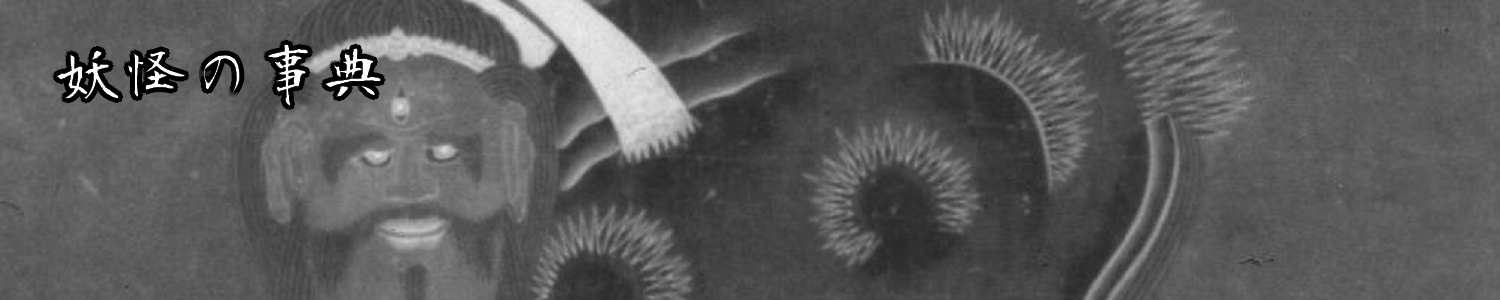|
【かっぱ】
日本各地に伝わる妖怪。
 河童の概要 河童の概要
河童は主に江戸時代に入って以降、様々な文献や画図に記録されてきた妖怪です。
民間伝承においても、北海道から九州に至るまでの広範囲に膨大な数の河童の話(或いは河童に類する特徴を持つ妖怪の話)が存在します。
川や沼などに棲む者とされており、その姿は子供のようだったり、猿、亀、カワウソなどの動物に似ているといいます。体の色は緑色で想像される傾向が根強く、頭には皿、背中には甲羅があります。
好物はキュウリや尻子玉(人の肛門にあると伝えられている玉)。相撲が得意ですが、頭の皿から水がなくなると力を失います。
ただし、これらの特徴はあくまでも現在一般的に広く知られている心象であって、地方や時代などによって様々な差異があります。
例えば、顔の色が青黒い河童もいれば、赤い河童もいます。鼻や口が鳥の嘴のようになっている河童もいれば、犬や猿のような形の河童もいます。頭に皿がない河童もいます。
好物もキュウリや尻子玉だけに留まりません。各地の伝承の中には、茄子を好む河童、桃を好む河童、カボチャを好む河童、玉蜀黍を好む河童、酒を好む河童、餅を好む河童などの話も見受けられます。また、『閑窓自語』には西条柿、『和漢三才図会』には人の舌を好むとあります。
一方、福岡県の柳川では、河童はキュウリを嫌うものだといわれます。泳ぐ際、かかとにキュウリのへたの匂いを擦り込むと河童が寄ってこないのだそうです。
鳴き声もいろいろで、青森県では「キャッ、キャッ」、岩手県では「ケ、ケ、ケ」、長野県では「グワァ、グワァ」、島根県では「ヨッ、ヨッ、ヨ」、九州では「ヒョー、ヒョー」と鳴くとされています。
人を水中に引き込んで溺れさせる怖ろしい妖怪としても語られますが、馬を引き込もうとして反対に陸地へ引き上げられてしまったり、厠で女の尻を撫でようとして手を切り落とされてしまい、涙ながらに謝罪するといった、どこか間抜けな一面も兼ね備えています。
 左甚五郎と河童 左甚五郎と河童
河童が誕生した経緯について、左甚五郎にまつわる伝説があります。
江戸時代の名工だった左甚五郎は、ある大名の館を建造する際、たくさんの藁人形に命を吹き込んで手伝わせました。そうして無事に館が完成したので、役目を終えた藁人形を川に流そうとすると、人形たちが訊ねてきました。「これからは何を食ったらいいのか」。甚五郎は「人の尻でも食え」と言って、彼らを川に流しました。
この藁人形たちが後々河童になり、人の尻子玉を狙いだしたのです。河童の腕は左右が繋がっていて、引っ張ると抜けてしまうといわれていますが、これも藁人形だった頃のなごりなのだそうです。
このような人形化生説の裏には、「川の民」「河原者」などとして蔑視されてきた人々への心象があるのだと思われます。
 河童名彙 河童名彙
河童名彙
|