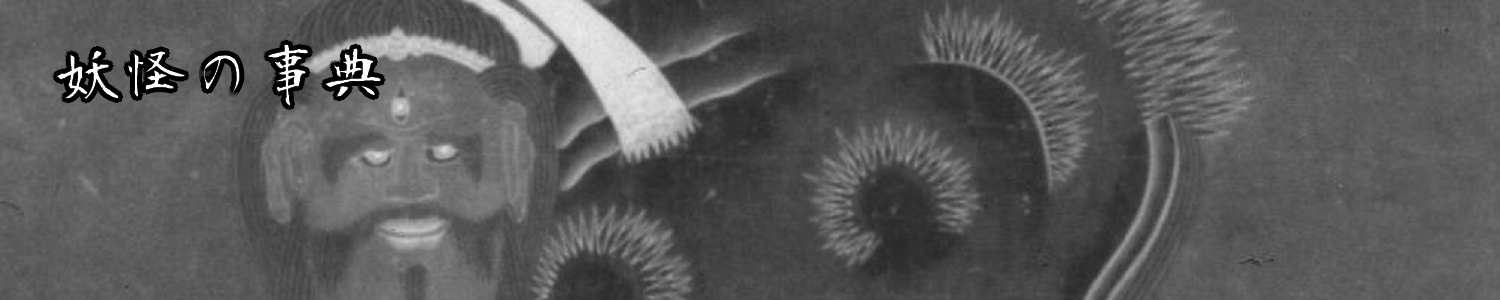|
【おに】
日本に伝わる妖怪。
中国では死霊のような存在を意味している「鬼」の字が、日本では「おに」に当てられています。
 鬼の概要 鬼の概要
中国
中国でいう鬼は、死者の霊のようなもの。
人間の魂魄は死後に二分され、魂は天上に向かい、魄は鬼と化すとされます。
日本
日本で一般的に想像される鬼といえば、頭に牛の角を生やし、腰には虎の皮をつけている、筋骨隆々の姿をした怪物です。
「桃太郎」「一寸法師」「こぶとりじいさん」といった有名な昔話に登場したり、節分の鬼やらいなど、鬼にまつわる行事があったり、さらには子供の遊びにも鬼ごっこがあったりして、日本人にとってよく知られた存在になっています。
しかし時代を遡ると、じつは「鬼」という呼称が現在よりももっと広い意味を帯びていたことが分かります。
霊的存在、力や気配、仏教に圧倒された土着の神。そして、漂着した異民族、体制に従わない人々までもが鬼と称されました。
多様な側面があった日本の鬼ですが、いつの世でもほぼ不変だったのは、鬼が記録者から見て「よくないもの」「恐ろしいもの」だったこと。
鬼とは要するに、霊的な感覚や社会の営みから生じた「負」の一表現だったと言えるかもしれません。
 日本の鬼の来歴 日本の鬼の来歴
語源
「おに」という言葉は、一説によると「隠」が語源であり、隠れて見えないことを意味していたとされます。
平安時代に書かれた『倭名類聚抄』にも、鬼は物に隠れて、現れることを欲さない故に、俗に「隠」と云われるという説明が見られます。
しかし、民俗学者の折口信夫はこのような「おに」を「隠」とする説に納得していなかったようです。
一體おにと言ふ語は、いろ/\な說明が、いろ/\な人で試みられたけれども、得心のゆく考へはない。今勢力を持つて居る「陰」「隱」などの轉音だとする、漢音語原説は、とりわけこなれない考へである。
『古代研究』第一部 民俗學篇 第一: 385-386ページ「信太妻の話」 折口信夫 1929
いずれにせよ、中国で用いられていた「鬼」の字が古代日本でも登用されると、次第に「おに」という読みが定着していくこととなりました。
奈良時代
『出雲国風土記』に大原郡阿用郷の地名の由来を記した文があり、その中に目一つの鬼なるものが登場します。ここで用いられた「鬼」の字に「おに」と読ませる意図があったかは定かではないそうですが、これが日本の文献における「鬼」の字の初出だとされます。
『日本書紀』には「鬼」の字が多く見られます。「斉明紀」にも、笠を着た鬼が斉明天皇の喪の儀を朝倉山から見ていたという話があります。
『万葉集』では、「鬼」を「もの」や「しこ」と読ませています。「もの」は超自然的な恐ろしい存在を暗示する語で、「しこ」は醜いという意味です。
平安時代
『倭名類聚抄』「鬼魅類第十七」は、鬼を俗に「隠」と云うと解説。さらに餓鬼、瘧鬼、邪鬼、窮鬼、魑魅、魍魎、醜女、天探女についても説明しています。
室町時代
酒呑童子を退治する物語を描いた『大江山絵詞』がこの頃に成立しました。
江戸時代
この時代になると現在と同じように、頭に牛の角を生やし、腰に虎皮をつけた鬼の姿が想像されるようになっています。こうした鬼の姿は、鬼が丑寅の方角から来ることにちなんでいるとされます。
鬼
世に丑寅の方を鬼門といふ 今鬼の形を画くには頭に牛角をいたゞき腰に虎皮をまとふ 是丑と寅との二つを合せてこの形をなせりといへり
『今昔画図続百鬼』上之巻 雨 鳥山石燕 1779
 鬼名彙 鬼名彙
各地に伝わる鬼の呼称(あるいは鬼に分類されることのある妖怪の呼称)を都道府県別に列挙します。
岩手県
悪路王
秋田県
ナマハゲ
長野県
八面大王
岐阜県
両面宿儺
三重県
大嶽丸
京都府
酒呑童子
大阪府
茨木童子
島根県
目一つの鬼
岡山県
温羅
徳島県
夜行さん
熊本県
鬼八法師
宮崎県
鬼八法師
|