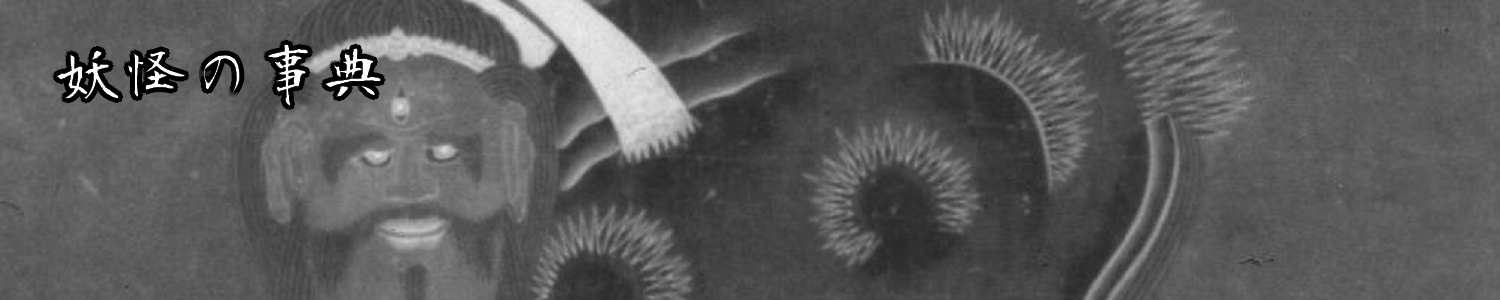
 牛鬼 牛鬼
|
【PR】
|
|
【うしおに】
西日本に伝わる妖怪。
 牛鬼の概要 牛鬼の概要
牛の頭と鬼の体、あるいは鬼の頭と牛の体という姿をしています。また、土蜘蛛の体として描かれたものもあります。多くの場合とても凶暴で、人や家畜に危害を加える恐ろしい牛の妖怪として語られますが、地方によっては怪火の類とされることもあります。
 牛鬼の伝承・逸話 牛鬼の伝承・逸話
和歌山県
熊野地方に伝わっています。
山の中で出会った者を見つめてくるそうで、牛鬼に見つめられた者は、終には疲れて死んでしまいます。これを「影を飲まれる」といって、そんな時は「石は流れる、木の葉は沈む、牛は嘶き馬吼ゆる」と、逆さごとを唱えれば回避できるといいます。
島根県
大浜村波路浦に伝わっています。
湯泉津湾外に一里ばかり、岸から一町のあたりで漁師が夜釣りをしていたら、岸の方向から「行こうか」と声が聞こえました。「来たけりゃ来い」と答えると、水中に何かが飛び込んできました。漁師はそれが牛鬼だと気がつき、慌てて舟を漕いで家へ逃げ込みます。家の外では押し入ろうとする牛鬼の怒号が聞こえましたが、気丈な妻が焼火箸で牛鬼の目をつくと、出雲大社のお札の効果もあったのでしょうか、牛鬼は逃げ去りました。
石見地方では濡女と協力して人を襲うとされます。
『異説まちまち』には出雲の国(島根県北東部)の牛鬼について書かれていますが、こちらは怪火の類のようです。雨が長く続いた時、白い光が体にまとわりつくことがあり、それを「牛鬼にあった」といっていたそうで、そんな時は火で炙れば消えるのだとか。
山口県
室積半島に伝わっています。
伊予の藤内図書という人が、弓術者の蔵喜兵衛尉と協力して牛鬼を退治したといいます。
徳島県
海部郡牟岐町に伝わっています。
白木山に牛鬼がいて、里に来ては人や家畜を食いましたが、鉄砲の名人がこれを退治したそうです。
愛媛県
宇和島では牛鬼祭が開催されます。とくに和霊神社の大祭がよく知られています。
 牛鬼の画図 牛鬼の画図
【牛鬼の画図が掲載されている主な資料】
| 資料名 |
作者 |
制作年 |
妖怪名 |
画像 |
| 『化物づくし』(個人蔵) |
不明 |
不明 |
牛鬼 |
|
| 『百怪図巻』(福岡市博物館蔵) |
佐脇嵩之 |
1737 |
うし鬼 |
画像 |
| 『画図百鬼夜行』前篇 風 |
鳥山石燕 |
1776 |
牛鬼 |
画像 |
| 『化物絵巻』(川崎市市民ミュージアム蔵) |
不明 |
1800年代前半? |
うし鬼 |
|
|

『百怪図巻』「うし鬼」 佐脇嵩之 1737
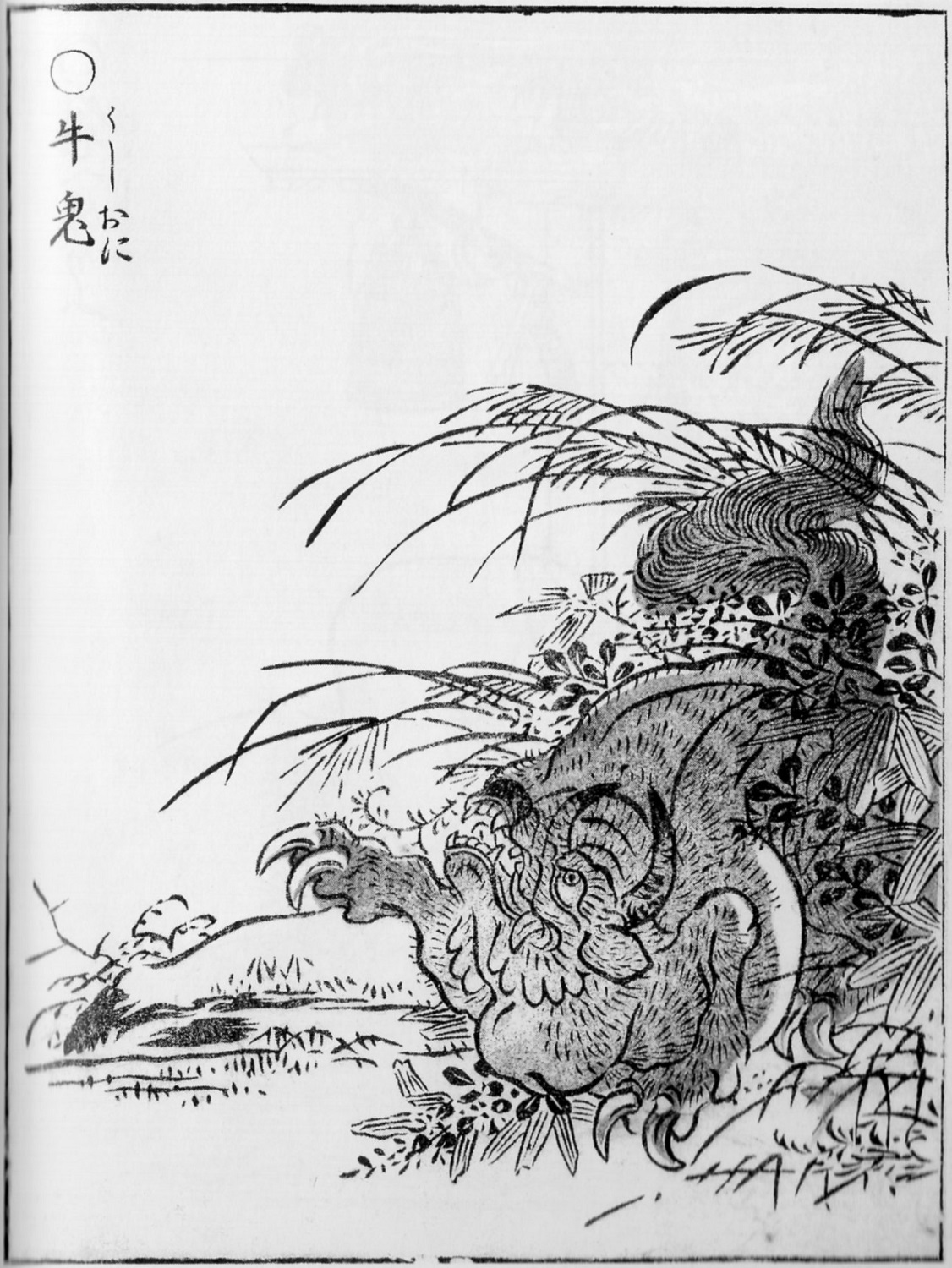
『画図百鬼夜行』前篇 風「牛鬼」 鳥山石燕 1776
|
|
 主な参考資料 主な参考資料
[文献]
『鳥山石燕 画図百鬼夜行』: 90ページ 高田衛 監修、稲田篤信 田中直日 編 国書刊行会 1992
『全国妖怪事典』(小学館ライブラリー): 161、169-170、183、188、201ページ 千葉幹夫 編 小学館 1995
『妖怪事典』: 52-53ページ 村上健司 毎日新聞社 2000
|

|


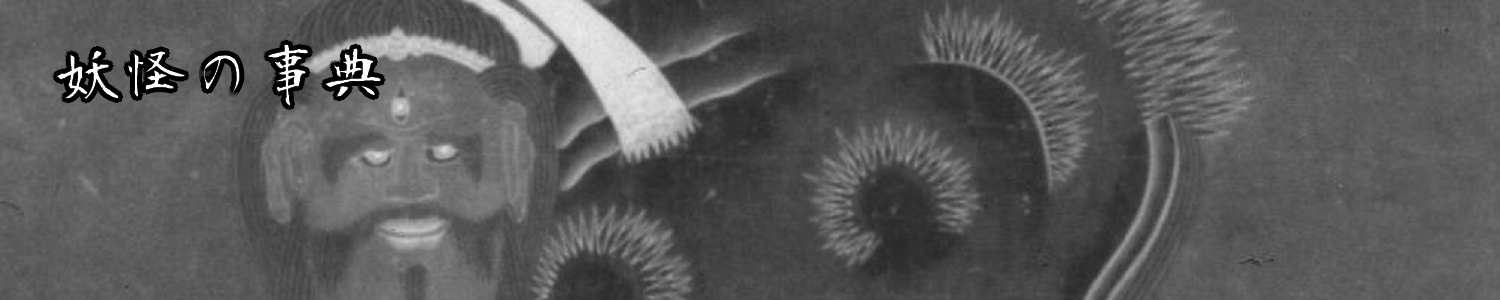
![]() 主な参考資料
主な参考資料