

|
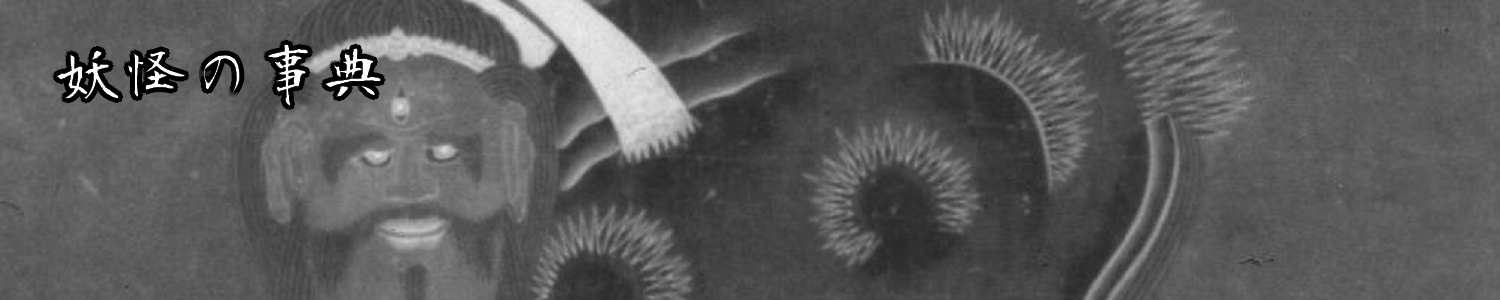
|
【PR】
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
江戸時代の絵巻や図譜にある妖怪。
|
|||||||||||||||||||||
| 資料名 | 作者 | 制作年 | 妖怪名 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 『化物づくし』(個人蔵) | 不明 | 不明 | ||
| 『百怪図巻』(福岡市博物館蔵) | 佐脇嵩之 | 1737 | しやうけら | 画像 |
| 『画図百鬼夜行』前篇 風 | 鳥山石燕 | 1776 | せうけら | 画像 |
![]() 主な参考資料
主な参考資料
[文献]
『鳥山石燕 画図百鬼夜行』: 78ページ 高田衛 監修、稲田篤信 田中直日 編 国書刊行会 1992
『妖怪事典』: 188-189ページ 村上健司 毎日新聞社 2000

|
【PR】楽天ROOM [妖怪]グッズコレクション | [妖怪]グルメコレクション | [妖怪]水木しげる グッズコレクション vol.1 / vol.2 / vol.3 | [妖怪]水木しげる グルメコレクション |