

|
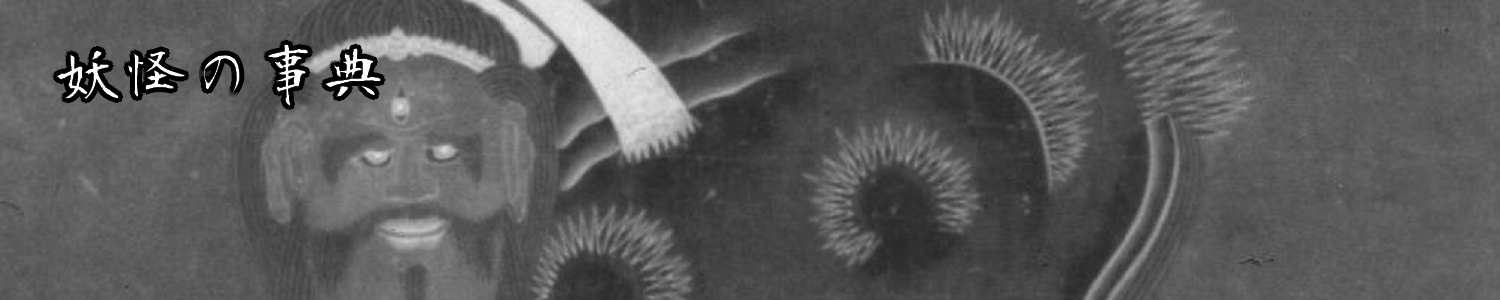
|
【PR】
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
【がごぜ】 大和(奈良県)の元興寺に出たという鬼。
|
|||||||||||||||||||||
| 資料名 | 作者 | 制作年 | 妖怪名 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 『化物づくし』(個人蔵) | 不明 | 不明 | かごぜ | 画像 |
| 『百怪図巻』(福岡市博物館蔵) | 佐脇嵩之 | 1737 | がごぜ | 画像 |
| 『画図百鬼夜行』前篇 風 | 鳥山石燕 | 1776 | 元興寺 | 画像 |
子供を脅かしたり、お化けを意味する言葉として、ガゴゼ、あるいはガゴゼに近い語彙が関東から西日本にかけて伝わっている。
ガンゴジ
ガゴゼ
ガゴゼ
ガゴゼ
ガゴゼ
ガゴゼ
ガゴジ、ガンゴジ
ガゴゼやガゴジという言葉がお化けという意味で使われるようになったのは江戸時代かららしく、由来はやはり元興寺の鬼だといわれる。ただし民俗学者の柳田國男の見解は異なり、「咬もうぞ」と言って現れることにちなむのではないかと考えていた。
![]() 主な参考資料
主な参考資料
[文献]
『鳥山石燕 画図百鬼夜行』: 85ページ 高田衛 監修、稲田篤信 田中直日 編 国書刊行会 1992
『妖怪事典』: 100-101ページ 村上健司 毎日新聞社 2000

|
【PR】楽天ROOM [妖怪]グッズコレクション | [妖怪]グルメコレクション | [妖怪]水木しげる グッズコレクション vol.1 / vol.2 / vol.3 | [妖怪]水木しげる グルメコレクション |